AXIES2024における会場ネットワークの裏側
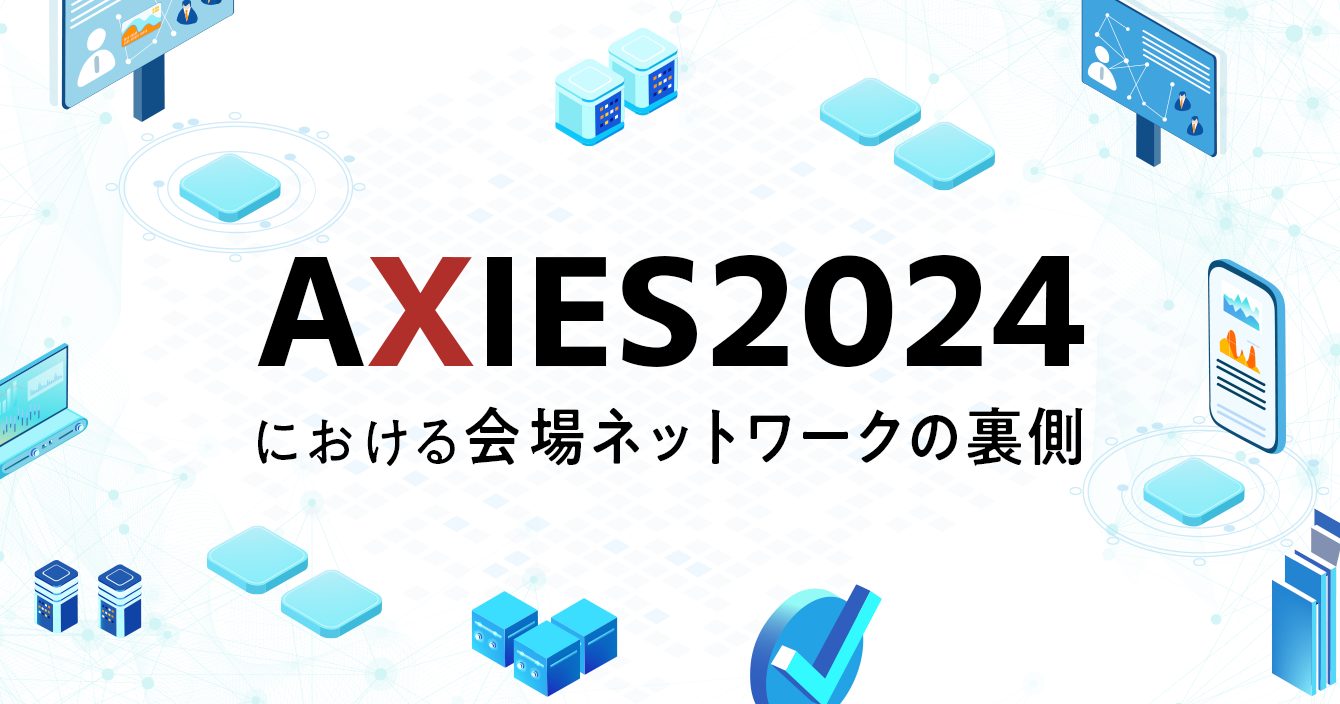
はじめに
2024年12月に奈良県奈良市でAXIES2024が開催されました。その会場ネットワークを、「BAKUCHIKU」NOCチームが構築・運用しました。さくらのクラウドを活用したAXIESにおけるNOC活動の様子を、チームの全体リーダーを務めた長崎県立大学大学院の早田と各チームリーダー(後述)が2回に分けて紹介します。
AXIESについて
AXIES(大学ICT推進協議会 / Academic eXchange for Information Environment and Strategy)は、高等教育・学術研究機関における情報通信技術(ICT)を活用した教育・研究・経営の高度化を図り、教育・学術研究・文化・産業に寄与することを目的とした協議会です。その中でも約1300名が現地参加するAXIESの「年次大会」は、ICTを活用した教育と研究の質の向上を目指し、大学間の情報共有と連携を促進する場として、年に一度開催されています。
BAKUCHIKUについて
BAKUCHIKUは2023年7月に長崎で開催されたJANOG52にて発足した会場ネットワーク構築・運用チームです。メンバーは毎回応募いただいた学生と社会人で構成され、割合としては毎回おおよそ半々程度となっています。JANOG以外に、今回のAXIESやCEDEC+KYUSHUなどのイベントでも会場ネットワークを担当した実績があります。今回は学生21名、社会人12名の計33名で構成され、奈良開催ということも相まってうち22名の方が関西方面から参加しました。
初めてJANOG以外で現地参加1000名を超えるイベントのネットワークを構築することとなりましたが、7月のチーム発足時に、「本番で片手間に本業や学業ができる程度に緩く活動する」ことを目標として定めました。この”緩く”という部分に様々なメッセージが含まれているのですが、主には膨大化するNOC活動の作業量や負担を減らし、学生や初心者の方にネットワーク構築の楽しさを経験していただくという意味でこのフレーズを使ったという背景がありました。
ネットワーク構成
今回構築したネットワークについての詳細を各チーム(バックボーン・サーバ・AP・ケーブル)ごとに紹介します。
BB (バックボーン) チーム
リーダー:吉川
メンバー:学生5名、社会人2名
役割:インターネットとの接続点とL3、L2スイッチの構築を担当
バックボーンチームリーダーの吉川です。BBチームを担当することになった当初、ネットワークといえばという部分であり、バックボーンが壊れるとすべてのチームへ影響を与えるので非常に重要度が高く責任のあるチームだなという印象がありました。私自身、今回のAXIESほどの規模の会場ネットワークは構築したことがなかったので、非常に多くのことを学ばせていただきました。ここでは、バックボーンの構成と当日の構築の様子を紹介します。
バックボーンの構成
今回のネットワークは、ルーターとL3スイッチがそれぞれ1台、L2スイッチが9台の非常にシンプルな構成になっています。インターネットへの接続は近鉄ケーブルネットワーク(KCN)様に10G 2本のLAGでご提供いただきました。
GW-RT01では、KCN様との接続 (static route)、VLAN間ルーティング、NAT、Firewall、さくらのクラウドへのVPN接続を行っています。GW-RT01には、Cisco様にご提供いただいたASR1001-HX-4GEを使用しました。L3スイッチにはNexus 93180YC-EXを使用し、VLANとLAGの設定を行っています。L2スイッチにはC9200L-24P-4GとC9200CX-12P-2X2Gを使用し、VLANの設定を行いました。
会場ネットワークを構築する上で、まず考慮すべき点としてケーブルの種類の選定が挙げられます。今回、インターネットへの接続が10Gであることから、ルーターとL3スイッチの間はLC-LCケーブルを使用しました。一方で、会場のMDFとEPSを接続するパッチパネルはSCコネクタかRJ-45コネクタであったため、L3スイッチとL2スイッチの間のケーブルはLC-SCケーブルまたはUTPケーブルを使用しました。これに合わせて、必要となるトランシーバの数も選定しました。
続いて、使用するアドレスの設計が必要です。グローバルアドレスはKCN様に割り当てていただいたので、BBチームではプライベートアドレスの各チームや用途ごとへの割り当てを担当しました。今回は、会場用プライベートアドレスとしてISP Shared Address(100.64.0.0/18)を採用しました。一般的に使われることの多いプライベートアドレスである172.16.0.0/12および192.168.0.0/16は、DockerのブリッジやVPNの接続先のアドレスと被る可能性があるため、それらを避けました。その他にゲスト用にDHCPで割り当てるセグメント、マネジメント用にAPやBBチームのネットワーク機器に固定で割り当てるセグメントやNOCチームのWiFi用のセグメントなどを決定しました。
また、ネットワーク機器の監視をするための設定も追加しました。監視方法としてはping監視のほか、SNMPを用いた監視やNetFlowを用いた監視にも挑戦しました。pingやSNMPによる監視はネットワーク機器に追加する項目は数行で終わり、サーバーチームによる可視化が、作業の大部分を占めていました。一方で、NetFlowによる監視は経験者が少なかったため、Cisco様のサポートを受けながら設定を進め、なんとか完成させました。最後に、実機は当日まで触ることができなかったので、事前検証としてさくらのクラウド上にCSR1000vを用意し、コンフィグの確認を行いました。基本的にコンフィグは準備期間に用意していたため、当日の実機投入は非常にスムーズに進めることができました。
ホットステージ
ホットステージの作業内容としては、まずお借りしている機器の確認から始めます。お借りした最初の状態の写真とシリアル番号を記録し、紛失や傷つけることがないよう管理していました。その後、ルーターに準備していた設定を投入していきます。本来ルーターでIPSec-VPNを設定し、さくらのクラウドとVPN接続をする予定だったのですが、機器をお借りする際に要件を伝え忘れており、ライセンスの問題でIPSecを使用できないという問題が生じました。そこで予備としてお借りしていたASR1001-Xを使用することにしました(こちらはライセンスが入っていました)。ASR1001-Xは10Gポートが2つであるため、下図のような構成に急遽変更しました。このような構成変更こそありましたが、その後の構築はスムーズに進み、ホットステージ中にさくらのクラウドとの接続を完了することができました。
L2スイッチはEPSおよび会場の隅に設置しました。EPSのL2スイッチはMDFに配置したL3スイッチと構内配線を利用して接続されます。そこからEPS内のパッチパネルに接続し、壁コンセントからAPに接続されるという流れになっています。L2スイッチをEPSのパッチパネルに接続するまでがBBチームの仕事で、壁コンセントとAPの接続はケーブルチームの仕事となります。
NOCを通して
準備期間2か月、会期1週間のNOCでしたが、技術面はもちろん、マネジメント面や他チームとの連携、会場ネットワークならではの考慮事項など、非常に多くのものを学べた期間でした。会期終了後のフィードバックでは「トラブルも起こらず安定したインターネットを提供できた」という一定の達成感を得ることができた一方で、「検証をもう少し早くしておくべきだった」ことや、「MDFで作業しており、チーム内で状況把握・コミュニケーションがやりづらい環境だったので、作業方法を見直す必要はある」といった改善すべきところも多数見つかり、各メンバーにとって収穫の多いNOCだったのではないかと思います。
サーバチーム
リーダー:中田
メンバー:森脇、城、前田、小林
役割:会期中にDNS、DHCP、監視を担当
はじめに
サーバチームリーダーの中田です。ここからは、サーバチームの取り組み内容について紹介したいと思います。サーバチームでは、会期中にDNS、DHCP、監視の3つのサービスを提供することを目的として活動しました。今回、すべてのサービスをさくらのクラウドで構築・運用しています。そのおかげで、現地での作業期間であるホットステージ前までに、最低限運用可能なサービスは構築が完了しており、余裕を持って作業に取り組むことができました。以降で、さくらのクラウドと会場間のサイト間VPNの設定や各サービスの設計について、各サービスを担当した中田、森脇、城、前田、小林が紹介します。
さくらのクラウド構成
今回、サーバチームはさくらインターネット様にご提供いただいた「さくらのクラウド」上に各サービスのインスタンスを構築しました。さくらのクラウドを初めて使うメンバーも多くいましたが、Webで簡単に、インスタンスの作成・起動・削除といった管理ができるので、慣れるのに時間はかかりませんでした。最終的に検証用も含めて、今回のリソース上限である20台のインスタンスを使用しました。さくらのクラウドと会場ネットワークの接続にはGREを使用しています。さくらのクラウド側のゲートウェイにはVyOSを使用しています。
DNS
DNS用のVMを2台用意しました。それぞれのVMに、DNSキャッシュサーバーであるKnot Resolver、PowerDNS Recursor、Unboundのコンテナを構築しています。dnsdistとkeepalivedを用いて、コンテナ間およびVM間の冗長化を行っています。
DHCP
Kea DHCPをホットスタンバイ構成で構築し、リース情報の管理にデータベースを導入することで、運用時の可用性と信頼性を向上させています。また、kea-exporterを導入し、現在のリース数をPrometheusとGrafanaで可視化しています。
監視
監視基盤の構成は以下のようになっており、メトリクスはPrometheusとGrafanaで、ログとNetFlowはSplunkで収集・可視化しています。
Prometheus & Grafana
メトリクスはPrometheusで収集し、Grafanaで可視化しています。主に以下のものを監視対象としました。
- ルーター・スイッチ・APの死活監視
- ゲートウェイルーターにおけるトラフィック量
- ルーター・スイッチの各インタフェースにおけるパケットのエラー数・ドロップ数
- 各APごとのクライアント数
- DNSクエリ数
- DHCPリースアドレス数
PING監視はblackbox_exporterを、SNMP監視はsnmp_exporterを用いています。
Splunk
Dockerで動作するDNSのログおよびNetFlowは、Splunkを用いて収集・可視化しました。SplunkはPrometheusとGrafanaが苦手とするテキストデータを処理することに長けているため、うまく使い分けができたと感じています。また、ミサイルマップやWord Cloudなど、多彩な可視化のためのテンプレートが存在しているので、さまざまな形式でデータを可視化することができました。
おわりに
今回はさくらのクラウド上でサービスを運用していたこともあり、現地に入る前にある程度構築作業を終わらせることができました。そのおかげもあってか、大きな障害に見舞われることもなく、無事会期を乗り切ることができました。短期間に集中してひとつのネットワークを作り上げるというのは、このようなNOC活動だからこそ体験できるものです。また、初対面のメンバーと準備期間や会期で密接に関わることになるので、同じ業界の人たちと仲良くなれる場にもなります。このような点から、とても貴重な経験になったと感じています。
APチーム
リーダー:丸岡
メンバー:学生7名、社会人1名
役割:会場の無線LAN環境の設計・構築・運用を担当
APチームリーダーの丸岡です。APチームは学生7名、社会人1名の計8名で構成され、会場の無線LAN環境の設計・構築・運用を担当しました。他チームと同様、約2ヶ月間の準備期間を経て3日間の会期中、参加者にPSK方式、OpenRoaming、eduroamという3種類の接続方式を提供しました。AXIESのような大規模なイベントでのAPの配置設計から構築、当日の運用は、メンバーのほとんどにとって初めての経験でしたが、チーム一丸となって取り組むことができました。その詳細についてご紹介します。
構成
今回、無線LAN環境を構築するにあたり、以下の機材をCisco様にご提供いただきました。
・WLC(Cisco Catalyst 9800-L-C-K9)2台 ※うち1台は予備機として待機
・WLC管理のAP(Cisco Catalyst 9120)45台 ※うち6台は予備機として待機
企業展示会場,セッション会場を中心に配置
・Meraki管理のAP(Cisco Catalyst 9164)10台 ※うち3台は予備機として待機
企業展示会場やセッション会場などからやや離れた全体会会場に全て配置
今回のネットワーク構築では、WLC管理のAPとMeraki管理のAPを物理的に異なる会場に分けて配置するという工夫を行いました。これにより、コントローラ間の干渉を避けつつ、トラブル発生時の切り分けを容易にすることで、迅速な対応が可能となりました。
また、無線LANサービスとして以下の3つを提供しました。
- 一般的なPSK方式(SSID: AXIES2024_BAKUCHIKU)
- OpenRoaming(SSID: AXIES2024_OpenRoaming)
- eduroam(SSID: eduroam)
これらのSSIDはWLC管理のAPとMeraki管理のAPの両方で提供しており、会場内を移動しても、参加者が同じ接続環境を利用できるようにしました。OpenRoamingの提供にあたっては、Cisco Spacesを利用しました。MerakiとCisco Spacesは直接連携できる機能を備えていますが、今回は設定がうまくいかなかったため、MerakiについてもCisco Spaces Connectorを経由して連携するように変更しました。また、eduroamの提供にあたっては、京都大学様からRADIUSサーバをご提供いただき、WLCおよびMeraki APからRADIUSサーバへのリクエストを通じて接続認証を実施しました。この構成により、OpenRoamingおよびeduroamを提供することができました。以下に、OpenRoamingとeduroamの構成図を示します。
事前準備
APチームは、約2ヶ月間の準備期間を通じて会場の無線LAN環境の設計と機器管理の準備を行いました。
AP配置場所の決定
APチームは、会場図面をもとに、チームリーダーがAP配置図の叩き台を作成し、チーム全体でレビューしながら補正を行いました。その後、機材数の調整に伴い、一部のAP配置を変更しました。最終的な配置は、会場の規模やレイアウト、参加者の動線を考慮して決定しました。
Cisco勉強会の実施
使用する製品に対するチームメンバーの理解を深めるため、Cisco様に2回の勉強会を実施していただきました。
- 第1回勉強会:Cisco Catalyst Wireless全般
- 第2回勉強会:Meraki概要、OpenRoaming/eduroamの説明
この勉強会では、機器の基本的な仕組みや管理方法、無線LANサービスの提供に必要な知識について学ぶことができました。また、運用上のポイントについても理解を深める大変貴重な機会でした。
役割分担の決定
事前に、APチーム内ではWLC担当(3人)とMeraki担当(3人)に分かれて作業を行うことにしました。それぞれの担当が、機器の管理や設定確認、運用準備に取り組むことで、本番でスムーズに作業を進めることができました。また、チームメンバーがCisco dCloudによるデモ環境にアクセスし、各担当のAPコントローラのダッシュボードを操作して確認する自主勉強会も開かれました。
ホットステージ
1日目〜2日目:機器の開梱と初期化
ホットステージの初日と2日目は、Cisco様から提供された機材の開梱と全APの初期化作業を行いました。開梱時には機材の管理を正確に行うため、全てのAPのシリアル番号、MACアドレス、ホスト名の対応表を、Notion上で作成しました。
3日目:インターネット開通とWLANの設定
3日目にBBチームの作業によってインターネット接続が可能となったところで、WLCおよびMerakiで本格的なWLANの設定・検証作業を進めました。
主な作業:
- APへの手動でのIPアドレス設定、WLCへのJoin
- PSK方式およびeduroamのWLAN設定投入と動作確認
- WLANが正常に提供され、接続および認証が正常に動作することを確認
- Cisco Spaces Connectorの設定と接続確認
4日目:APの設置とOpenRoamingの設定
4日目は、会場全域に配置図に基づいてAPの設置作業を実施しました。今回APを設置するにあたりスタンドを使用しましたが、転倒のリスクを考慮してウェイトで固定することにしました。
主な作業:
- 事前に作成した配置図を基にしたAP・ポスター設置作業
- APとLANケーブルの接続
- OpenRoamingの設定投入と動作確認
APの設置後、会場の全域でWLANが安定して提供されていることを確認しました。
運用
会期中3日間にわたって無線LAN環境の運用管理にあたりました。WLC担当とMeraki担当がそれぞれのダッシュボードでAPの状態や、PSK方式、OpenRoaming、eduroamの接続状況をチェックしました。Ciscoの方によるアドバイスなどを基にRSSIやチャネルボンディングの設定を行い、初日の状況を踏まえ2日目以降は2.4GHz帯の運用を停止し、5GHz帯のみでの運用に切り替えることで、通信品質の向上を図りました。加えて、Wi-Fiアナライザを使用して会場内を巡回することで、電波状況の調査も行いました。接続トラブルや不具合の報告には、会場内に設置したポスターに掲載したGoogle Formsの問い合わせフォームを活用しました。問い合わせがあった場合は、現地調査や設定変更により対応しました。WLC管理のAPとMeraki管理のAPは物理的に異なる会場に配置していたため、トラブルの切り分けはスムーズに進めることができました。
まとめ
私を含め多くのメンバーにとっては、初めて大規模なイベントでAPの配置設計から構築、運用までを一貫して担当するという、とても貴重な経験でした。初めてならではの課題も多く、手探りな部分もありましたが、結果として十分な無線環境を提供することができ、大変うれしく思います。私個人としては、限られた準備期間の中でチーム全員が効率的に作業を進める体制を整え、会期中はさまざまな状況に応じた対応を行うチームリーダーとしての経験を積むこともできました。また、NOC活動終了後にフィードバック会を行うことで、接続の安定性向上やチーム内での認識のすり合わせなど、今後改善が必要な課題も見つけました。今回の経験を今後のNOC活動に活かし、より快適なネットワーク環境を提供できるよう取り組んでいきたいと考えております。
CB(ケーブル)チーム
メンバー:山下、市毛
役割:ケーブルの設計・作成・敷設・運用管理を担当
ここからは、CB(ケーブル)チームの山下と市毛が感想なども交えながら、印象深い作業の内容についてお話ししていきます!
全体スケジュール
CBチームのチーム設立から会期後までのスケジュールは以下の通りです。
| 日程 | 作業内容 |
|---|---|
| 定例MTG (毎週木曜日(10/6~計9回)) | 配線図・結線表の作成 必要物品の洗い出し、整理、発注 ケーブルの作り方、養生の仕方、などの勉強会 会場でのスケジュール作成、確認 |
| Day-3 | 物品の確認作業、ケーブル切り出し作業 |
| Day-2 | ケーブル切り出し作業、成端作業&テスター検査 |
| Day-1 | 成端作業&テスター検査、タグ付け作業、仕分け作業 |
| Day0 | 敷設作業 |
| Day1 | 見回り、補強、追加配線、変更配線 |
| Day2 | 見回り |
| Day3 | 見回り、撤去作業 |
事前準備
CBチームでは、Slackのハドル機能やNotionを使用しながらミーティングを行い、事前準備を進めました。
配線図作成
はじめに、ケーブルの本数・長さ・配線ルートを検討するために、配線図の作成に取り組みました。配線図を作成するまでの流れとして、まずはAPチームが「APをここに置くべ!」と配置場所を提案。それを受けたBBチームが「じゃあSWはここだな」と配置場所を決めます。CBチームでは、「どんなルートでケーブルを通そうかな?」とみんなで頭をひねりながら、手分けして配線図に描画しました。今回は単にAPへの配線だけでは終わらず、展示ブースや配信機材への有線提供という追加ミッションも発生し、その結果、気づけば合計ケーブル数が70本超えの見積もりに。「これ、3日で撤収するんだよな……」という思いを胸に抱えつつ、全員で地道に作業を進めました。
結線表作成(ケーブル長の算出)
どのケーブルがどの機器に接続しているのかを明確化するために、結線表の作成に取り組みました。とはいえ、全部を自力でやるのは無理なので、結線表の土台を作成した後は、機器のホスト名などの記入をBBチームやAPチームに「お願いしますね!」と依頼し、それと配線図をもとにケーブル長を一本一本算出する作業に、突入しました。メンバーの中には、縮尺図をA3印刷して定規で測るという建築家スタイルを採用した人もいました。しかし、「これ、パソコンでできたらいいよね」となり、途中からdraw.ioを活用してデジタルで測定する流れになりました。メンバーそれぞれが時間を見つけて作業を進めたり、ミーティングが早く終わった時にチームで確認しながら進めていきました。70本以上のケーブルを一本一本算出するこの作業は、とても地道で大変なものでした。しかし、この地道な作業は、どれくらいのケーブルを購入する必要があるのかを決定する重要なプロセスです。そのため、手を抜くことなく、着実に進めていきました。
山下:一人で作業する中で不安に感じる場面があったり、draw.ioでピクセル単位で計測した結果、とんでもない長さになっていたりと、確認の重要性を実感しました。
ケーブル作成
切り出し作業
ホットステージが始まり、まず物品確認を行い、その後ケーブルの切り出し作業に取り掛かりました。今回、切り出したケーブル長は合計で約2000mにも及び、ミニ奈良マラソン1周分ぐらいになります。300m巻きのケーブル8箱を用意し、必要なケーブル長ごとに切り出していきました。その際に長いケーブルから順に切り出すことで、無駄を最小限に抑えるように工夫しました。また、切り出すと同時に、8の字巻きでまとめる作業も行いました。実は、切り出した後の8の字巻きが大変でした。
今回の最大ケーブル長が75mであり、また余長を多めに取ったことから、比較的長いケーブルが多くありました。最初はケーブルの長さやねじれ(キンク)が原因で8の字巻きに苦戦しましたが、繰り返し作業を重ねることで、次第に効率よく巻けるようになりました。特にケーブルが短くなるにつれて、スムーズに8の字巻きができるようになり、作業が安定していきました。また、今回使用したケーブルは茶色と水色のもので、ケーブルのねじれ(キンク)がしっかりついているものもあり、8の字巻きが難しかった印象です。
成端作業+タグ付け
ケーブルの切り出し作業が完了した後、いよいよ成端作業に移りました。この工程では、切り出したケーブルにRJ45コネクタを取り付け、テスターを用いて試験する作業を行いました。今回は現地成端ということもあり、品質保証の観点からフルーク社の機器を使用しました。また、RJ45プラグとして貫通型と非貫通型の2種類を用意しました。通常はどちらか一方に統一する方が自然な気もしますが、今回は学びと経験の観点から2種類のコネクタを採用しました。事前MTGの段階でメンバーの成端経験を確認したところ、成端の経験がないメンバーや、貫通型のみ、あるいは非貫通型のみ経験があるメンバーがいることが分かりました。そのため、貫通型コネクタと非貫通型コネクタについて学び、経験してもらえる絶好の機会と考え、あえて2種類を採用しました。
さらに、成端直後とタグ付け作業の前の2度に分けてフルークで試験を実施しました。品質保証の観点からも重要ですが、「某NOGの某NOCチームで、『知らんけど精神』でテストしなかった結果、断線ケーブルが多発したんだよね〜」という報告から、ダブルチェックを徹底しました。また、成端後のケーブルを会場ごとに仕分けし、作成予定のケーブルを全て作れているかの再確認を行いました。さらにテプラを使ってケーブルタグを作成し、全ケーブルの両端に取り付けました。具体的には、各LANケーブルに対応する機器の名称(結線表にあるAPやSWなどと番号を含めて一意に識別できるように)と、その接続機器に割り当てるべきポート番号をCSVファイルに書き込み、テプラで印刷し、印刷したシールを両端の近くに貼りました。
山下:私が担当したのは50mから始まり、45m、40m、35mという感じでしたが、50mと45mの本数が多かったことから、そこでだいぶコツをつかむことができ、40mあたりから早くきれいに巻けるようになりました。作業過程でねじれの取り方もなんとなく分かるようになり、スムーズにケーブルを巻けるようになったことが、「ケーブルチームらしくなってきたなぁ」と感じる瞬間でもありました。結果として、延べ2000mにも及ぶケーブルを切り出し、8の字巻きでまとめた作業の成果は、以下の写真からも感じられるように壮観でした。また、私自身はこれまで両タイプのコネクタを使用して成端作業を行った経験があり、今回も改めて両方を使用してケーブルを成端しました。貫通型コネクタでは、銅線をコネクタに通した際に配線の色順を確認しやすく、銅線を確実に奥まで通すことができた一方で、長めに解線した銅線をコネクタに挿入する作業には手間取ることがあり、時には銅線が曲がってしまう場合もありました。非貫通型コネクタでは、銅線を通した後に色の順番を確認しづらい点や、適切な長さに調整してからニッパーで切る作業も必要で、貫通型と比べて慣れが必要でした。
市毛:私は成端作業の途中から参加したのですが、初めての成端作業であり、丁寧に教えていただいたことで何とか作業ができました。
配線作業全体
敷設作業
事前に作成した配線図とスケジュールをもとに敷設作業を実施しました。会場全体を使用できるのは会期前日の1日だけだったため、効率的に作業を進めるための準備を徹底しました。作業人数の不足を補うため、近鉄ケーブルネットワーク(KCN)様に助っ人を依頼し、約10名で連携しながら対応しました。環境に応じて養生テープ、センタードライテープ、トラテープ、ゴム養生を使い分け、臨機応変に配線を敷設しました。特に配線量が多い展示ブースやドア周辺の敷設作業は、脚立を活用するなどして安全かつ効率的に実施しました。その結果、会期中の断線などのトラブルは発生しませんでした。
会期中の見回りと対応
会期中は、定期的に見回りを行い、断線や養生テープの剥がれがないかを確認しました。必要に応じて養生の補強を行い、安定した配線環境を維持しました。また、AP(アクセスポイント)の配置変更や追加設置が必要な場面にも迅速に対応し、追加配線や配線変更を実施しました。すべての作業においてKY(危険予知)活動を徹底し、安全確保を最優先に進めました。
撤収作業
撤収時には、敷設作業時と同様に役割分担を明確にし、サーバチームにも協力を依頼して効率的に作業を進行しました。脚立を使う作業も含まれるため、KY活動をCBチームとサーバチームで合同で実施し、安全を確保しました。また、大量のケーブルを8の字巻きで整理し、梱包作業を迅速に完了させました。その結果、撤収作業はスムーズに終了しました。
山下:大量のケーブルを回収し、8の字巻きするのはとても大変でしたが、このメンバーでの最後の作業かと思うと少し寂しくもありました。最後の方では少しでも疑問に思ったら連絡する!ということができ、ちゃんとチームの一員として動けていたかなと思います。また、撤収後に欲しいケーブルをみんなでもらったり、ちょっと余裕がある他チームの人がかしめ作業体験に来るなど交流も行えました。この1週間で15mや20mのケーブルを短いと感じてしまうようになったのが面白かったです。
まとめ
山下:私は今回メンバーとして参加したのですが、リーダー陣2人が事前にいろいろな情報を集めてスライドにまとめてくださったおかげで、チームメンバーが動きやすかったです。また、当日も指示出しをしてくださり、円滑に作業を進めることができました。しかし、リーダーに仕事が集中していたのが改善点であるという反省も出ました。メンバーそれぞれ次のNOCで活かしていけたらと思っています。作業中もさまざまなことがありましたが、このチームで本当に良かったです!
イベントを終えて
BAKUCHIKUとしてJANOG52からの活動を通してナレッジは蓄積されていたものの、JANOGとはまた異なる部分で困難に直面することも多くありました。また、ホットステージ中は問題なくネットワークを運用できていましたが、本番になりクライアント数が増えるにつれて、各チームで問題が発生し、そのトラブルシューティングに勤しむ場面もありました。しかしながら、特に最終日などはこれまでのNOCと比較してもかなり余裕を持って活動できていた印象です。加えて、何より参加していただいた学生メンバーの方から「楽しかった」「またNOC活動をやりたい」と言っていただけたため、当初定めた「本番で片手間に本業や学業ができる程度に緩く活動する」という目標を達成することができたのではないかと考えています。
また、学生が全体リーダーという立場を務めて感じた点を少しだけお伝えすると、これまでのNOC活動では見えていなかった(そもそも見ようともしていなかった)部分での苦労が多かったです。チームを発足させる際のマネジメントの難しさや、メンバーが心理的安全性を確保した状態で快く活動できるようなチームの土台作りにかなり気を配りました。BAKUCHIKUに限らず、他のネットワーク構築チームでもこのような背景の上に“気持ちの良いチーム活動”が成り立っていることを身をもって経験することができ、良い機会だったと感じています。
おわりに
AXIES2024では、当日のネットワーク品質について不安定さはあったものの、結果としては概ね問題なく会場ネットワークを提供することができたことを大変嬉しく思います。他大学の学生や社会人メンバーのサポートはもちろん、事務局の皆様や回線・各機材を提供いただいた企業様のご協力あってこその成功だったと感じています。活動を支えてくださった皆様にあらためて心より感謝を申し上げます。是非、BAKUCHIKUや他コミュニティでの活動を通して「ネットワークの楽しさ」を知るきっかけにしていただければ幸いです!