さくらのAIハッカソン レポート~高専生が考える身近な課題解決~
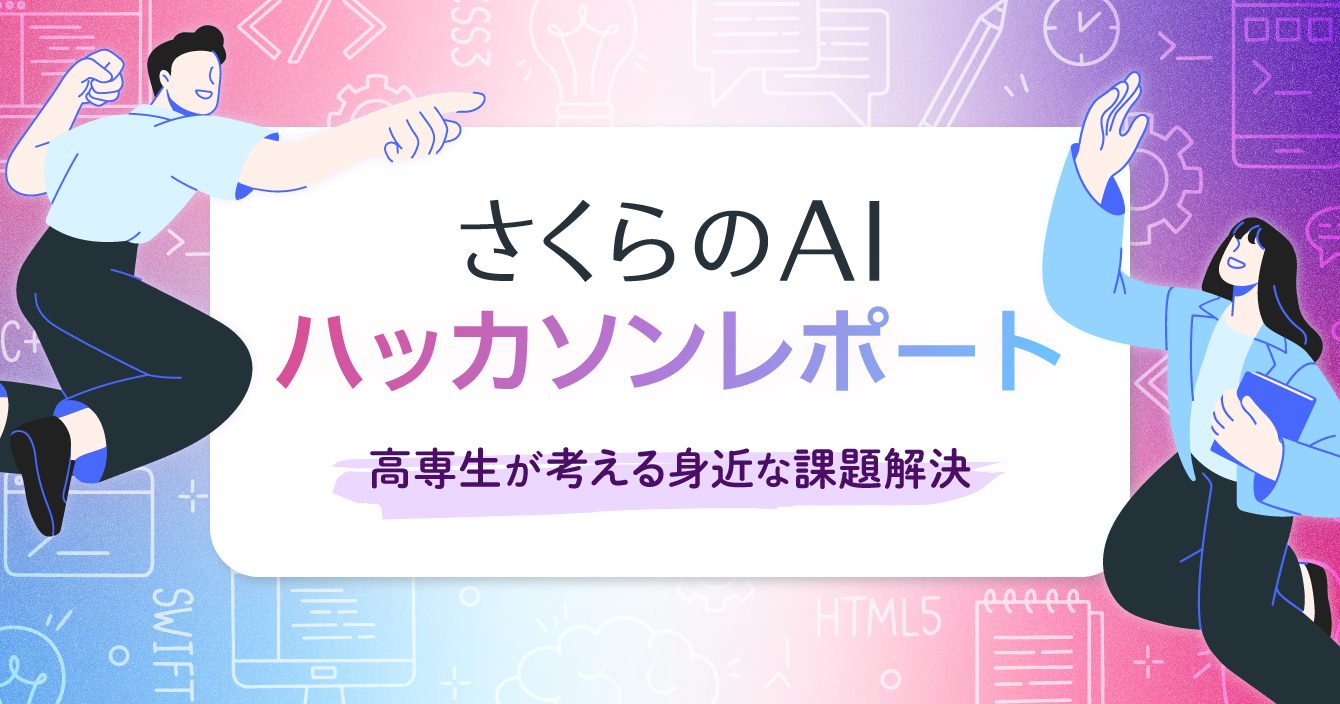
こんにちは、さくらインターネットの大喜多です。2025/8/30(土)に、第1回さくらのAIハッカソン with Kloudの成果発表会がおこなわれましたので、その様子をレポートいたします。
目次
オープニング
「アイデアを形に!生成AIで作る次世代プロダクト」をコンセプトに、高専生がチームまたは個人で10日間の開発期間でプロダクト開発に挑みました。
審査は、「独創性/新規性」「実装(デモの完成度)」「AI活用力」「実用性」の4つの観点で採点され各賞が決定します。
9つのチームがプレゼンテーションを行いました。
- Nisshi
- vive cording
- pepperoni
- kisarazu*Delta
- ロールキャベツ
- natsune
- AIを使うよ(決意)うにお願いします(注文)
- am9:21
- あいうえお
審査員は株式会社miiboの功刀様と、さくらインターネット株式会社からは小笠原と角が担当しました。
ここからは各チームのプレゼンテーションについて紹介していきます。
AI学習プランナー/Nisshi
Nisshiでは、AI学習プランナーと呼ばれるアプリケーションを開発しました。利用者が得意科目・不得意科目などの情報を入力することで、AIが学習スケジュールを作成してくれるというものです。開発は主にバイブコーディングを用いて行ったとのことで、開発時点からAIを活用していたことがわかりました。
メンバーは全員アプリケーション開発未経験ということで、アプリケーションを開発するためには何が必要か?という点から、AIを用いて調査することからはじめたといいます。
LLMで実現する高精度株価予測/vibe cording
vibe cordingでは、LLMを用いて株価予測を行うアプリケーションを開発しました。企業に関する様々な情報を学習させることで、より精度の高い株価予測を実現しようというものです。デモンストレーションでは、従来の株価予測との比較が紹介されていました。株価予測を行うためには有価証券報告書全文などの多くの情報を学習させる必要があることも紹介されていました。
DailyProof/pepperoni
学習を習慣化するためのアプリケーションを開発しました。AIが学習プランを作成し、学習の証拠を写真としてアップロードすることで、AIが学習目標の達成を判定し、スマートフォンが使えるようになるといったアプリです。やはりスマートフォンの存在が学習習慣の妨げになっているという意識はあるようです。
AIパートナーと始めるパスファインディング/kisarazu*Delta
パスファインディングとは、「やるべきことの管理」と「目標の設定および達成」そして「モチベーションの維持」などを行うことです。
毎日のタスクを把握し、モチベーションを維持しながら目標へ向かう手法とのことですが、これを人力で行うのは難しいため、コンピューターにて行うツールを開発したとのことです。
TC-Scopeと呼ばれるアプリケーション群は「毎日のタスクを確認・どの順番で進めるべきかを管理するTask-Scope」「夢や目標を実現させるためのステップをAIと考えるChallenge-Scope」「タスクや目標を共有しモチベーションを上げるStellar-Scope」の3つに分かれています。初のWebアプリ開発ということで大変だったとのことですが、今後にも生きる有益な経験となったようです。
編入PATH/ロールキャベツ
高専から大学に編入するという作者は、「編入試験は過去問が少ない」という課題を感じ、AIを使って想定問題を作成するアプリケーションを開発したとのことです。実際にデモも行われましたが、複雑な数式もWebで正しく表示できている点はすごいと思いました。一方で、問題の質は過去問をすべて学習させるなどしないと精度が向上しないという課題を抱えているようでした。
NeconoTe/natsune
パソコンで文章を書く際に「半角/全角」ボタンを押して日本語入力と英数字入力を切り替えることはよくあることですが、こと技術ブログとなると頻度が多くなりがちです。そこで作者はAIを使って入力した文章を整形してくれるブラウザ拡張機能を開発しました。
具体的には以下の画像のように変換ができるようになっています。実際にデモも行われ、文章が自動変換されるさまを見ることができました。
特定の固有名詞を事前に登録しておいて変換精度を上げるなどのカスタマイズにも対応しています。
DO OR DOOM/AIを使うよ(決意)うにお願いします(注文)
こちらも目標管理のアプリケーションですが、特徴的な点としては、タスクを達成した場合と達成しなかった場合の絵日記をAIに生成させることで、よりよい未来へのイメージを想起させるという点でした。
Vibe Cording流行ってる(断定)けど、実際どうなの?/am9:21
Vibe Cordingは生成AIを使ったコーディング手法ですが、手を動かしている時間と待っている時間が交互に発生するという問題があるとしました。
これを以下のように細切れの時間も有効活用して生産性を上げようというのがこのアプリケーションの目的になります。
細切れを時間をどう有効活用するかについては、アイデア出しの時間にすることで有効活用するというアプローチをとりました。実際に動いているデモも行われましたが、このデモ環境はデータが消失してしまったために1日で復旧させたものだということで、デモの途中に修正作業なども行われるといった異色のデモとなっていました。
Okosite/あいうえお
※編集部注:発表者の希望により、写真にモザイクをかけています。
「高専生は朝起きられない」と語る作者は、朝起きられるためには「無機質なアラーム音ではなく人から話しかけられるようにすれば起きられる」と着想し、AIと合成音声を使って起こしてくれるアプリケーションを開発しました。
デモでは、かわいらしい合成音声によって起こしてくれる様子を見ることができました。
審査の時間を経て、各賞の発表
すべてのチームの発表が終わったあとに審査員による審査が行われ、各賞の発表の時間になりました。
AI活用賞(さくらインターネット賞)には、AIによる文章変換を実現したnatsuneのNeconoTeが選ばれました。おめでとうございます。審査員の角からは「非常にシンプルに作業の生産性に貢献するアイデアで、AIもすごく活用されていて素晴らしいなという風に思いましたし、今後の内容とした点も非常に楽しいかなと思いますので、選ばせていただきました」とコメントがありました。
続いて優秀賞の発表です。
優秀賞には、Vibe Cordingの空き時間を有効活用するアプローチをとったam9:21の佐⁺⁹が選ばれました。おめでとうございます。審査員の功刀様からは「隙間時間ってものすごく課題だなと思っていました。なるほどと思って、楽しみだなと思いました。活用ももちろんそうなんですけれども、発表の時間が余ったからその場で直して動かそうというのがすごいと思いました。プロダクトもこれから楽しみですし、ハック魂がすごいなと思いました。」とコメントがありました。
そして最後に最優秀賞の発表です。
AIと合成音声によって起きるというアプリケーションを開発したあいうえおのOkositeが選ばれました。おめでとうございます。審査員の小笠原からは「日常的なところにAIを入れるってこれからすごい大事なことだと思っていて、50代は調べ物にしか使っていないが、10代は自分のことをものすごく教えているというデータがあって、それをよく表していると思いました。」とコメントがありました。
審査員講評
小笠原:ハッカソンの審査員、コロナ禍までは結構やっていたんですけど、最近は全然やっていなかったのですが、すごい楽しくて。さくらインターネットとしても、もっとハッカソンやった方がいいと思っているので、もしやったら皆さんには次回も出てほしいと思います。先ほども触れましたが、無理に見つけた課題じゃなくて身近なところの課題解決をしているというのがいいと思います。または、課題解決を飛ばしてすごく大きなテーマをAIを使って実現するというのも思ってもらえると、これからも面白いものができるのじゃないかと思いました。
功刀様:ハッカソンを見ると、自分も開発したくなりますし、今日すごくいいなと思ったのは、AIが出てきて、プログラミングにあまり触れていなかった方がハッカソンにチャレンジして、アウトプットに挑戦するというのは、すごく素敵だなと思いました。私自身も個人開発やハッカソンなどでプロダクトを出して、それで生まれた素敵な出会いとか、つながっていって仕事になるとかいうことがありまして、皆さんも出したプロダクトをいろんな人に触ってもらって輪が広がっていくと面白いことが起きるんじゃないかと思いましたので、ぜひ引き続きやってもらうといいかなと思いました。
角:非常にレベルの高い発表が多くて、賞を選ぶというのも苦労したところでありました。本当に素晴らしい作品が多かったなと思っています。AIでバイブコーディングができるようになってきたことで、日々の課題とか持っているアイデアを形にすることの敷居がものすごく下がってきたのかなと思います。今回も初めてプログラミングをしたというような方もいらっしゃったと思うんですけど、そういう中でアプリケーションを作りきったということは、以前よりもかなり回転数を上げられる状態になったのではないかと思いますので、これからもどんどん開発をしていただくと面白いものが出てくるんじゃないかと思いました。さくらインターネットとしてもそういった取り組みをお手伝いできればと思いました。
懇親会
成果発表会のあとは懇親会が行われました。
懇親会では審査員の角よりさくらインターネット賞の授与が行われました。
まとめ
審査員の皆さんもおっしゃっていましたが、非常にレベルの高いプロダクトが多く出ていました。また、身近な課題解決に取り組んでいるというのも社会人をしていると忘れがちなことなので非常に新鮮に感じました。今回ハッカソンに出場した皆さんには、これからもプロダクト開発を続けていってほしいなと思いました。
「さくらのAI Engine」パブリックリリースされました!
このハッカソンで使われた生成AIプラットフォームが、「さくらのAI Engine」として2025/9/24にパブリックリリースされました。無料枠もありますので、この機会に是非触ってみてください。またさくらのナレッジでは、「さくらのAI Engine」を紹介した記事も掲載していますので参考にしてみてください。